毎年年末が近付くと、会社から配られる年末調整の書類。
「よくわからないけど、とりあえず提出している」という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、年末調整に関する基本的なことや注意点を、サラリーマン視点でわかりやすくまとめました!
年末調整とは?
年末調整とは、会社があなたの1年間の所得税を正しく計算し直してくれる手続きのことです。
私たちの毎月の給与から天引きされている所得税は、実はざっくりとした概算です。
そのため、年末時点で「実際の年収・家族構成・保険料の支払いなど」を反映して、正しい税額を再計算する必要があります。
具体的には、以下のような情報をもとに計算されます。
・年収
・扶養親族(配偶者やお子さんなど)の有無
・所得控除(生命保険料控除、社会保険料控除など)
この再計算によって、払いすぎていた税金が戻ってくる(=年末調整還付)こともあります。
つまり、正しく書類を提出することで「損しない」ための大事な手続きなんですね!
年末調整でやること!
年末調整では、次の書類を会社に提出します。
これさえ出しておけば、あとは会社がすべて計算してくれます!
1.扶養控除等(異動)申告書
この申告書には以下の内容を記入します。
・扶養している家族(配偶者・お子さんなど)
・障害者控除
・寡婦控除 ひとり親控除
・勤労学生控除 など
これらの控除を申告しない場合でも、提出は必須です!
提出しないと、税金が多く引かれてしまうので注意!
2.基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
…はい、とっても名前が長い1枚の用紙です。笑
この書類では、以下のような情報をまとめて申告します。
こちらの書類も、すべての方に記載していただく資料になりますのでしっかり確認しておきましょう!
・基礎控除
すべての人が対象となる基本の控除です。
ただし、合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に控除額が減額され、2,500万円を超えると控除が受けられなくなります。
なお、令和7年度税制改正により、基礎控除の見直しが行われる予定です。
・配偶者控除、配偶者特別控除
配偶者の年収が一定以下の場合に受けられる控除です。
配偶者控除 → 配偶者の収入が48万円以下
配偶者特別控除 → 48万円超~133万円以下の場合など
・特定親族特別控除
令和7年分から新たに追加された控除です。
具体的な対象や要件は国税庁の資料等で今後も確認が必要ですが、扶養親族の中でも大学生のお子さんなどを扶養している場合に該当することがあります。
・所得金額調整控除(給与が850万円以上など条件付き)
こちらは、以下のいずれかに当てはまる方が対象になります。
・給与収入が850万円超
・扶養親族の中に23歳未満の子どもがいる
・本人や配偶者、扶養親族が特別障害者
条件に当てはまる場合、税金の負担を軽くするための調整が入ります。
3.保険料控除申告書
こちらの書類には、年間で支払った各種保険料などを記入します。
具体的には以下の控除が対象です。
・生命保険料控除(生命保険 介護医療保険 個人年金保険)
生命保険、介護医療保険、個人年金保険が対象となります。
保険会社から送られてくる「控除証明書」を貼り付けて提出します。
・地震保険料控除(自宅の地震保険)
自宅の地震保険料などが対象となります。
・社会保険料控除(お給料から天引きされている社会保険料、国民年金、国民健康保険)
こちらには、自信で支払った国民年金や国民健康保険などを記載します。
なお、お給料から天引きされている社会保険料につきましては、こちらに記載する必要はございません。
・小規模企業共済等掛金控除(企業型年金、iDeCoなど)
企業型確定拠出年金(DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo)などが該当します。
控除を受けるためには「控除証明書」が必要になることがほとんどです。
毎年、10月頃に届く書類を年末までしっかりと保管しておき、年末調整の書類に添付して提出しましょう!
4.その他
・住宅ローン控除(2年目以降の方)
住宅ローン控除を受ける方で、2年目以降の人は「住宅借入金等特別控除申告書」を会社に提出する必要があります。
こちらの申告書は、1年目の確定申告後に税務署から送られてくる用紙です。
また、1年目につきましては、確定申告が必要になるため忘れずに行いましょう!
これらの書類を提出すれば、あとは会社の担当者がすべて計算してくれます!
慣れない言葉がたくさん出てきますが、しっかりと控除を受けるためにも記載漏れのないようにしましょう!
年末調整での注意点!
上記では年末調整でやることについてご紹介しましたが、実は年末調整だけでは控除できないものもあります。
こういった控除を受けたい場合は、別途「確定申告」が必要になります。
以下によくある代表的なケースをご紹介します。
1.ふるさと納税(寄附金控除)
ふるさと納税をした場合、その寄附額の一部が「寄附金控除」として所得税・住民税から差し引かれます。
しかし、年末調整だけではこの控除を受けることができません。
ただし、「ワンストップ特例制度」を使えば、確定申告をせずに控除を受けることができます。
この「ワンストップ特例制度」につきましては、別記事で詳しく解説予定です!
2.医療費控除
1年間で支払った医療費が一定額(10万円or所得の5%超)を超えた場合、医療費控除の対象となります。
これも年末調整では控除を受けることができないため、確定申告が必要になります。
3.住宅ローン(1年目)
住宅ローン控除は「2年目以降」は年末調整で手続き可能ですが、1年目だけは確定申告が必須です。
忘れずにご自身で申告しましょう!
まとめ
・年末調整は、会社があなたの1年間の所得税を正しく計算し直してくれる手続きです。
多くの場合、払い過ぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります!
今年(令和7年)はさらに、基礎控除、給与所得控除の拡大があるため、例年と比べて還付額が増える可能性があります。
・年末調整を受けるには、会社に以下のような書類を提出する必要があります。
扶養控除等申告書、基礎控除等申告書、保険料控除申告書 など
・年末調整だけでは控除できないものがあります!
ふるさと納税、医療費控除、住宅ローン控除(1年目)などは確定申告が必要になります。
以上!サラリーマン目線での年末調整解説でした!
これからもお金に関すること一緒に学んでいきましょう!
【 注意事項 】
※本記事は一般的な制度について解説しています。詳細な税務処理や個別の状況については、税務署や税理士にご相談ください。

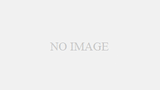
コメント